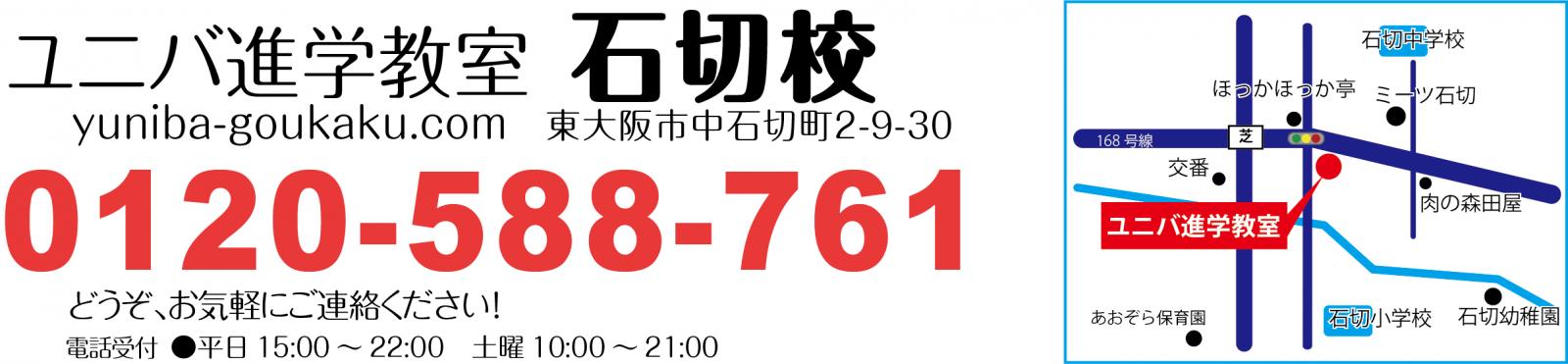3000円分の入塾お祝い金プレゼント!
英才個別指導で「生き抜く力」を育てます。
-
自習室無料wifiつなぎ放題
-
無料体験お子様に合わせた、学習方法を一緒に探していきましょう。 見学や、体験授業も随時行っております。
-
定期テスト対策入塾前の中2の学年末テストで英語の得点が8点だった生徒は2ヶ月後の中間テストでは82点をとることができました。
-
入塾試験今勉強に悩んでいたり、できない科目があっても心配いりません。できるようになりたいという気持ちがあれば必ず学力は伸びます。
- 東大阪市立石切中学校[東大阪市]
- 東大阪市立孔舎衙中学校[東大阪市]
- 東大阪市立石切小学校[東大阪市]
- 東大阪市立孔舎衙小学校[東大阪市]
- 東大阪市立孔舎衙東小学校[東大阪市]
- 東大阪市立石切東小学校[東大阪市]
キャンペーン情報



塾からのメッセージ
勉強すれば視野が広がります。
例えば、「コップに半分入ったお茶」を見て、「半分も」か「半分しか」か、どのように感じるかは、その人の立場や思想、文脈によりますね。こういった背景を想定する力も国語力の一環です。
半分って何グラム? と疑問を持てば算数が始まりますし、放っておいたら、量や質に変化があるのか? と仮説を立ててみると、理科の勉強が始まりますね。また、このお茶の原産地は静岡かな? と思いを馳せられると社会の勉強が始まるのです。
考えてみれば、自転車が走るのに、本当に必要な道路の幅は、ほんの数センチです。しかし、そんな道路は危険ですし、不安で走れません。よそ見もできないし、寄り道もできない。勉 強というのは道路を広げるのと一緒なのです。そして、寄り道こそ、人生の最大の楽しみではありませんか。こんなもんは将来の役に立たないと思うかもしれない。確かにそうかもしれない。できなくても生きてはいけるかもしれない。それでも、できる方が、より楽しく生きられることは間違いありません。
「常に生産性のある日々を」
私の好きな言葉です。
ぜひ、ユニバ進学教室石切校で共に学びましょう
料金体系
【高校生】4,820円/月~
【中学生】4,480円/月~
【小学生】3,250円/月~
特別対策講座
英才個別指導
-----------------------------------------------------
◇◇◇英才個別指導とは?◇◇◇
本当にお子さまに望むことは学力向上や成績アップでしょうか?
もちろんそうなのですが、私たちは、本物の教育がお子様にあたえるものは、教え、わからせたことの先にあると考えています。それを得るために、勉強というものを通じて、その先にあるものを見据えた自学力、問題解決力、克己心などの「人間力」をトータルに養っていく必要があるのではないでしょうか。
◆ユニバの「英才個別」は、お子様の「できる力」を引き出します
このような悩みをお持ちの小学生の保護者様
①「答えを見つけるため」ではなく「ひらめきを育てる」学習をさせたい。
②「集中力がない」「家で学習できない」
③ 計算問題はできても文章問題ができない。
④「本」を読まない。「本」を読めない。
⑤ 小学校の学習だけでは不安。
◆このような悩みをお持ちの中高生の保護者様
①「家庭学習のやり方」がわからない。「家で学習しない」
②「テスト勉強のやり方」が分からない。
③「学校の成績」を短期で上げたい。
④「少ない宿題」で成績を上げたい。
⑤「クラブ活動」をしながら塾に通いたい。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。お子様に合わせた、学習方法を一緒に探してゆきましょう。見学や、体験授業も随時行っております。