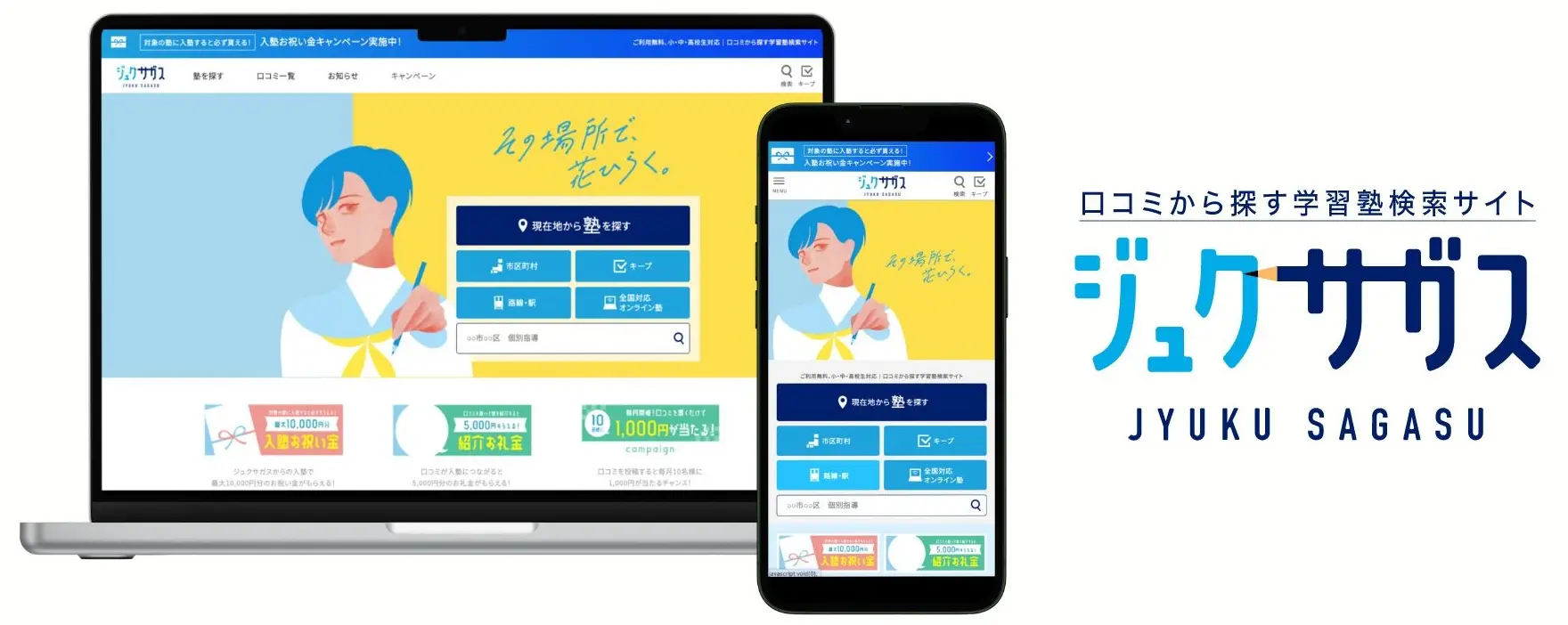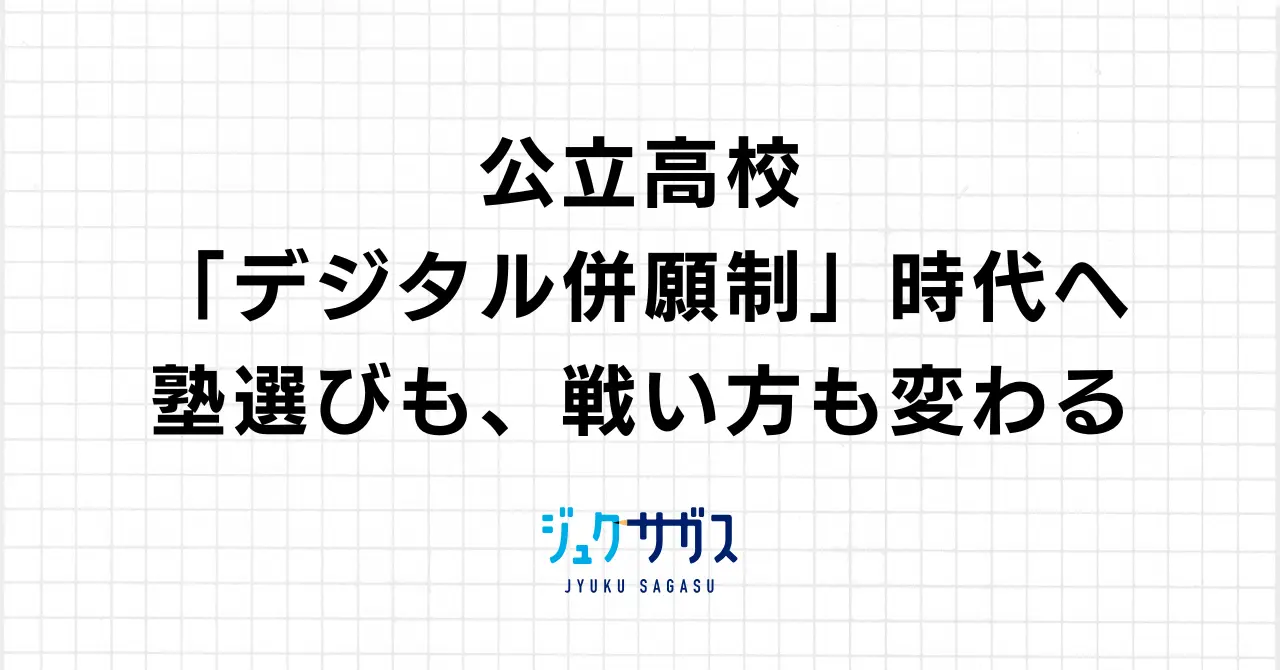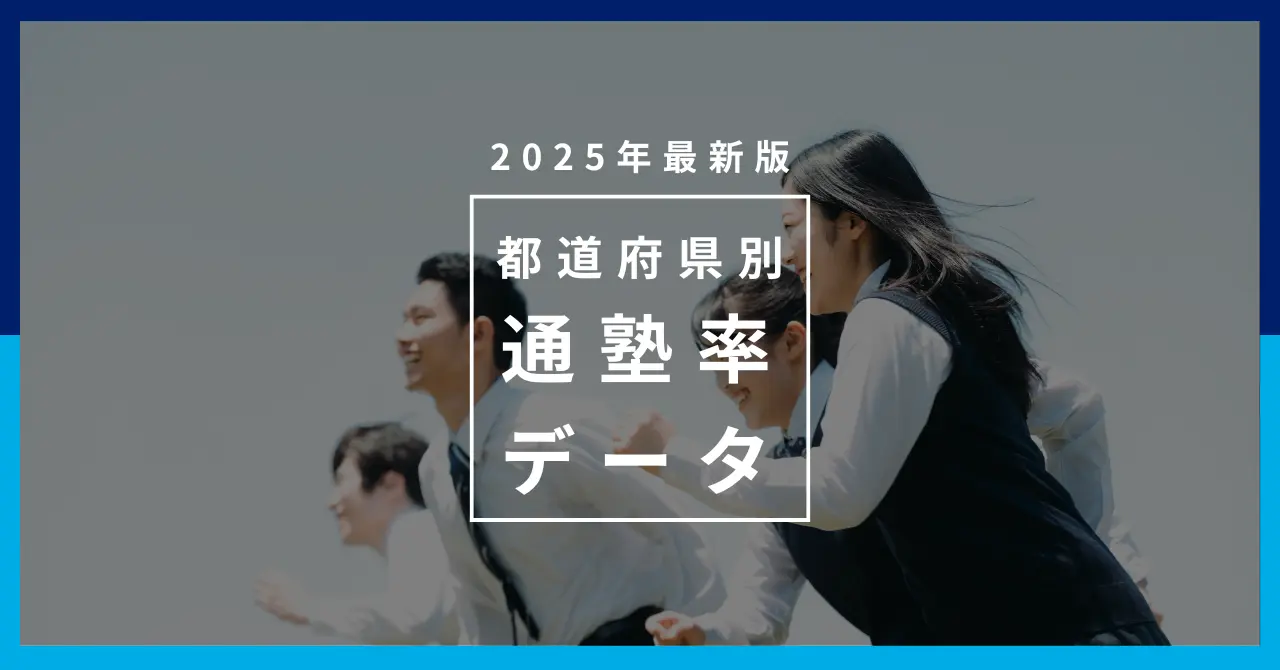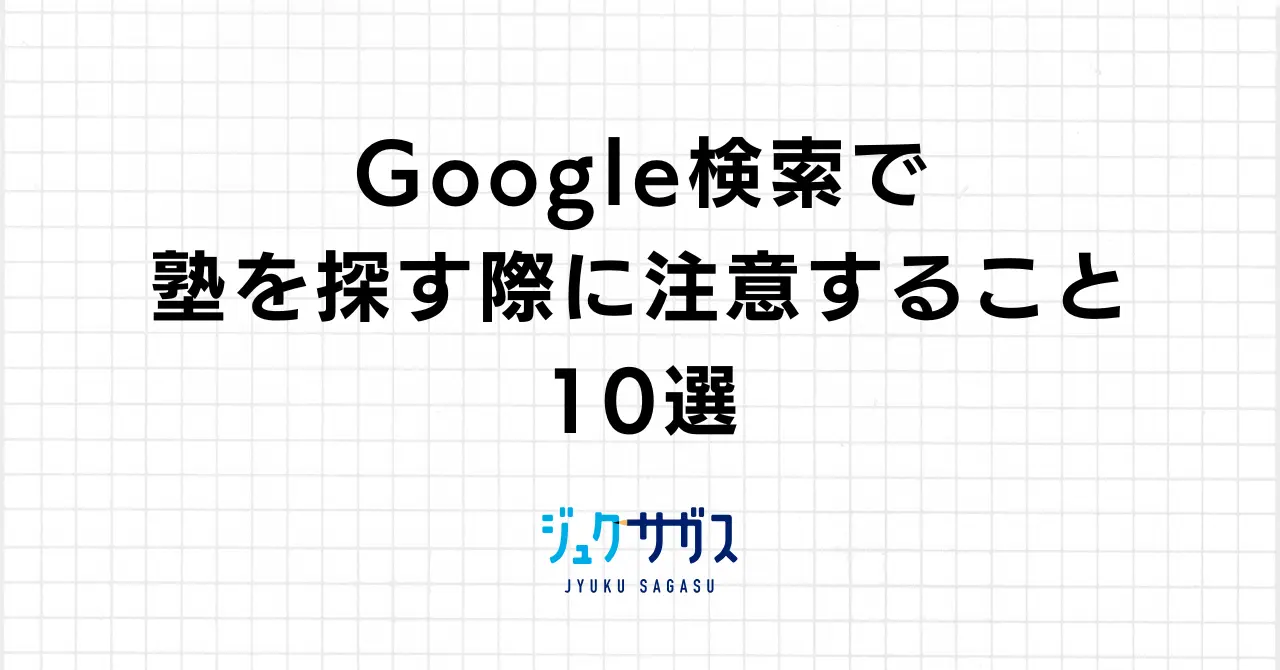「どこを受けるか、1つに絞らなきゃいけない」——そんな時代が、今まさに終わろうとしています。政府が導入を検討している「デジタル併願制」により、公立高校でも複数校を志望できる制度へと移行していく可能性が高まっています。これは、子どもたちの選択肢を増やすだけでなく、保護者の塾選びの考え方にも大きな変化をもたらします。今、保護者が知っておきたい塾との向き合い方を、じっくり掘り下げていきます。

「第一志望しか出せない」時代の終わりと、広がる選択肢

これまで多くの地域では、公立高校を受ける際に一つの学校しか出願できない「単願制」が主流でした。しかし、新制度では、複数校を志望でき、試験結果と内申点から最適な進学先が自動的に決まる仕組みが想定されています。
これにより、「挑戦校」「実力相応校」「安全校」といったように、受験に戦略性が加わります。受験がより「計画的」になり、子どもの可能性を広げやすくなるのです。
塾の役割も、「合格させる場所」から「進路を一緒に考える場所」へ
この変化により、塾に求められるのは“授業力”だけではありません。次のような力がますます重要になります。
- 志望校の優先順位を一緒に考えるカウンセリング力
- 試験だけでなく、内申点を意識したトータルの学習設計
- 学校ごとの特色や傾向を踏まえた対策の引き出しの多さ
つまり、模試の偏差値やテスト対策だけでは見えない、“受験全体を見渡す視点”を持つ塾こそが、これから信頼されていく存在になります。
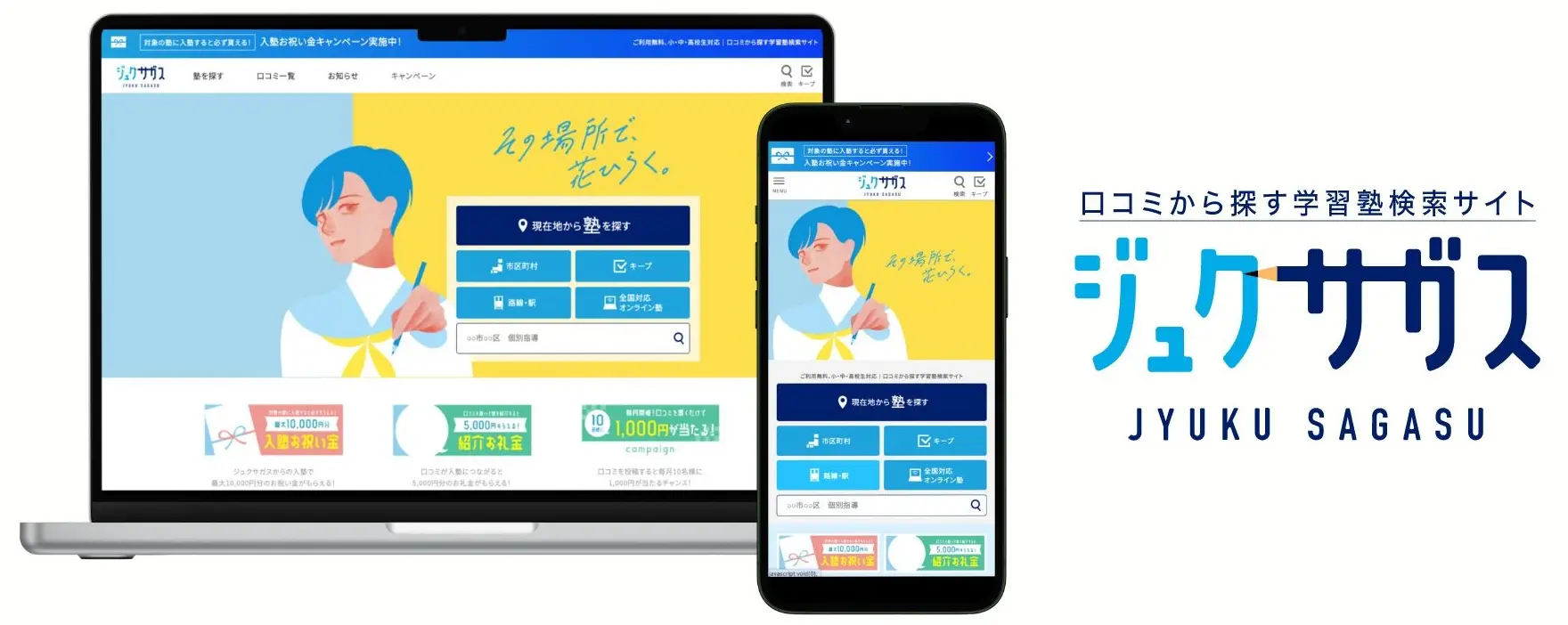
ICTでもカリスマ講師でもなく、“見てくれる人”がいる塾を選ぶ
最近は、ICT教材や大手塾のブランドに惹かれる方も多いですが、大切なのは“うちの子に合っているか”という点です。特にデジタル併願制のように柔軟な受験が可能になる中では、次のようなサポートができるかが鍵です。
- 志望校ごとに対応した個別の対策
- 日々の提出物や授業態度をフォローする内申点サポート
- 定期的な三者面談やLINE相談などの「心の距離の近さ」
いわば、子ども一人ひとりの“受験の物語”に寄り添ってくれる塾こそが、親として安心して任せられるパートナーになっていくはずです。
塾選びは、点数の上がり幅だけで決めない

受験制度が変わると、どうしても「どの塾が対応しているか?」という視点に傾きがちです。でも、それだけでは本質を見失ってしまいます。重要なのは、制度が変わっても変わらない「子どもの気持ち」「塾との相性」。受験制度に強い塾を探すのではなく、“この子の個性と未来”に強い塾を選んでください。
親として、迷ったときの基準はとてもシンプル。「この塾に通わせたら、この子が前向きになりそうか?」です。
制度が変わっても、寄り添う姿勢が変わらない塾を
公立高校の受験制度が柔軟になることで、子どもたちはこれまで以上に“自分の意思”を表現できるようになります。塾選びも、そんな子どもの意思を引き出し、信じ、導いてくれる場所であるべきです。
大切なのは、「制度の波に乗れる塾」よりも、「変化の中でもぶれずに一緒に歩んでくれる塾」を見つけること。そんな場所に出会えたら、制度の変化はきっと味方になってくれます。